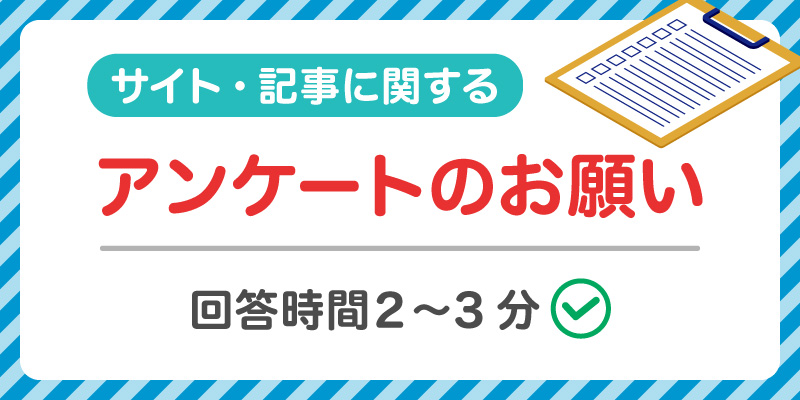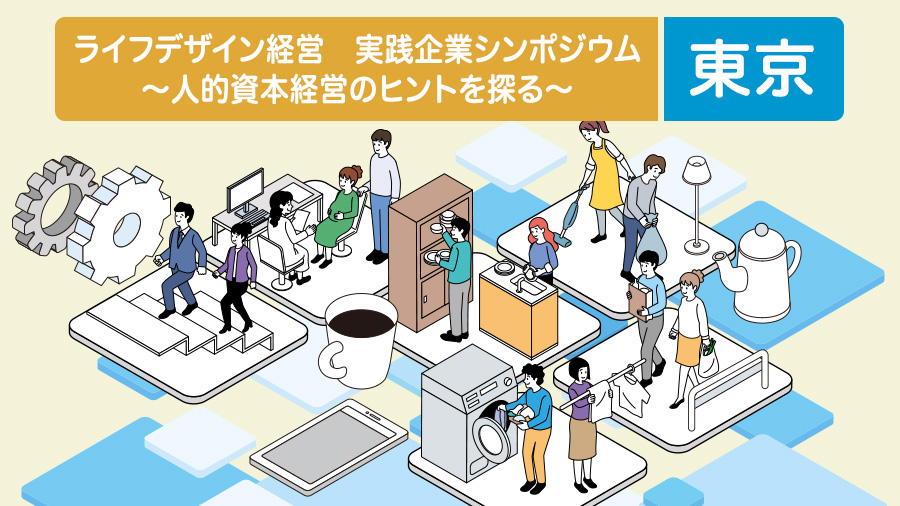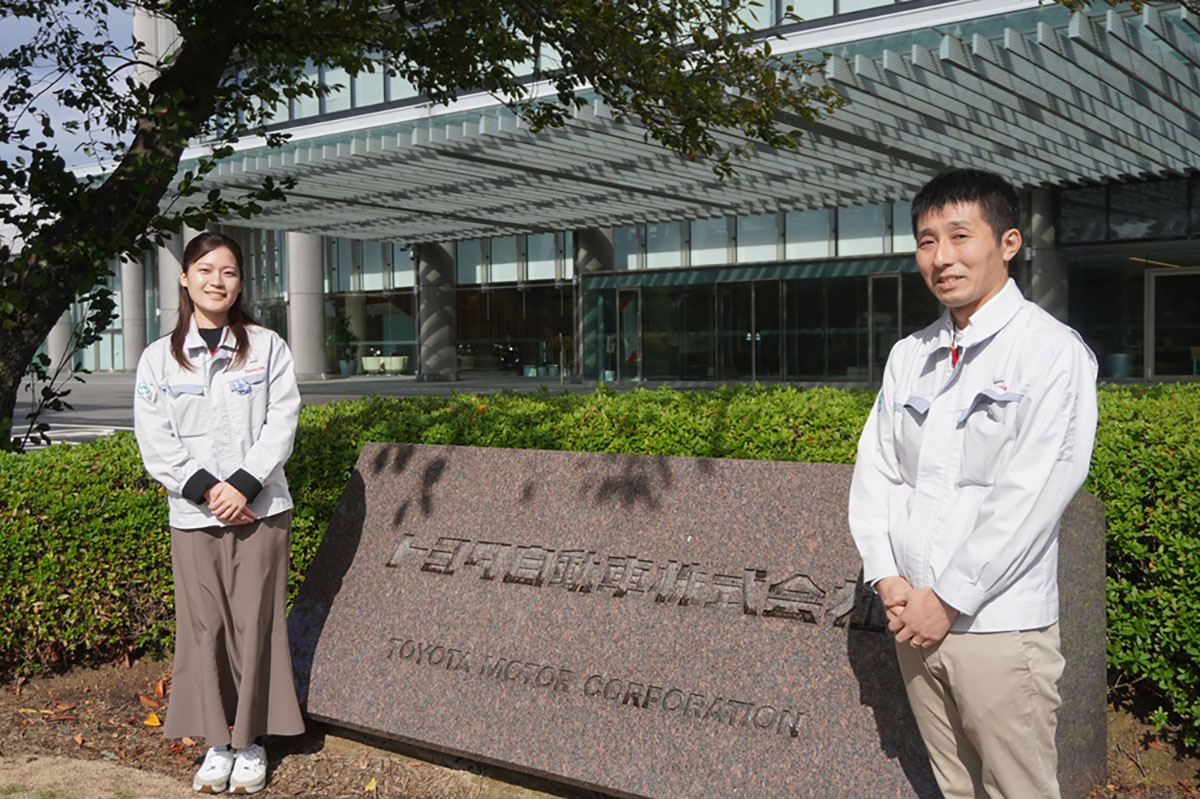「子育て施策」から本当の働き方改革を通じ働きがいを実現
株式会社フジワラテクノアート
日本酒や焼酎、しょうゆ、みそを造る麹醸造機械で国内シェア8割を持つ株式会社フジワラテクノアート(岡山市、社員159人)は、働き方改革を通じて社員の自律的な取り組みを引き出し、事業拡大につなげている。時間にとらわれず働く社員が出世しやすかった従来の人事評価を見直し、職位に求められる技能を明確化することで、時短社員でも昇進・昇格を目指せるようにした。社員の納得感を高めるため、社員の評価は全役員が出席する評価会議で、所属長が説明する。「オーナー企業にありがちな『好き・嫌い』人事の誤解を持たれないように徹底したことが、多様な人が自分らしく活躍できる職場の風土につながっている」。こう口をそろえる創業家でもあるフジワラテクノアート副社長の藤原加奈氏と、採用担当取締役の藤原由佳氏に、話を聞いた。
記事のポイント
- 納得される人事評価に向けた昇格基準の明確化。人事評価は、全役員参加の会議で理由を説明し、「好き・嫌い」を排除
- 人事評価とビジョンを掛け合わせ、会社の成長につなげる会社と社員のエンゲージメントを実現
- 裏方的な位置づけだった人事総務部門も、価値を創造する部門に
- 「個人別5か年ビジョン」策定し、多様な“個”がリスキリングなどを経て新しい可能性を生み出す環境を会社が用意
- 本当の働き方改革を通じ、社員が助け合う職場風土が定着

■反発の中で時間をかけて進めた人事の見直し
フジワラテクノアートの働き方改革への着手は、2016年にさかのぼる。当時、同社は、男性社員が90%弱を占め、専門性の高い技術者が個人商店のように仕事をし、「残業をはじめ、時間を問わずに働く人が評価される会社だった」と、加奈氏は振り返る。一方、「働き方改革への着手当初、社員向けの支援策も女性活躍の文脈が重視されて子育て支援が多く、男性の働きやすさも考えなければ会社の成長にはつながらないという問題意識があった」とも語る。
同社は2016年に社員、人材に力点を置いた新たな経営理念を刷新し、17年に連動する形で人事制度を作り直した。複雑だった社内の資格等級制度は、顧客ニーズへの対応はもちろん人事や総務といった社内業務も含め、柔軟に対応する「非定型業務」を自律的に遂行できる人材を評価することで、目立つ成果を上げる営業職ばかりが評価されるのではなく、多様な“個”の力の発揮につながっているという。
人事評価の公平感が高まることで、これまで従属的な業務と位置付けられていた社員も自身の仕事に主体的に向き合うようになり、採用担当役員の由佳氏は、「新しい業務改革といった提案も出てくるようになり、社員の雰囲気が変わった」と話す。
当初は、大幅な人事の見直しに、シニア層を中心に「クビを切るためなのか!」と強い反発もあったが、社員との対話機会を設けるなどして資格等級の定義を明確にすることで、「本当に必要な人材とはなにかを明言化し、 「オーナー色の中小企業では人事が『好き・嫌い』で行われているように誤解を受けやすい。そういったこともなくすことができた」(由佳氏)という。
■社員の成長を支えスペシャリスト集団をつくる「個人別5か年ビジョン」
もっとも、人事制度の見直しで、同社の雰囲気が一気に変わったわけではない。同社は昇格基準の明確化に加えて、会社が目指すべき方向性を明確にする「開発ビジョン2050」を2018年に策定した。加奈氏は、「経営者と従業員の意見が違うのは当然。だからこそ目線合わせが必要」と語る。2023年から始めた社員個人の強みや特性をいかす「個人別5か年ビジョン」の策定もその一つだ。成果・目標や行動目標を「will(やりたい)-can(できる)-must(すべき)」シートを使いながら、策定する。一人ひとりの目標を明確にすることで、社員をスペシャリスト集団として育てていった。
「経営者がいくら頑張ってビジョンを作っても、後ろを振り向いたら誰もついてきていないでは、意味がないんです」と、加奈氏。由佳氏も「大事なことは、会社と社員の目線合わせ。こうした取り組みが業績を一気に高めるものではないけれど、信頼を積み重ねることが大切だと思います」と話す。
いまでは、技術部門、社内外の調整役を担うコーポレートコミュニケーション部門、製造部門などすべての部門でスペシャリスト化が進み、多様な能力と過去の経験・実績を持った人材がそろってきた。「クライアントの要望に応えるためには、1人でできることは限られます。横の連携がどれだけできるか。多様な個の掛け合わせで、新しい可能性が出てくると思います」と加奈氏。社員それぞれが、やりがいや向上心といった内発的動機から仕事と向き合ってもらえる環境づくりを進める。

■会社と社員をつなぐコンピテンシー
コンプライアンス、チームワーク、創造性、礼節――。
同社は10のコンピテンシー(行動指針)を策定している。
約1500社の取引先との実績の中で、業績のほとんどが取引先の要望に応じたオーダーメイドの機械であり、自分で考え、判断できる自律した社員を求めている。コンピテンシーを通じて、「どういう人が昇格するのか明確になることで、仕事の『質』で評価する風土が定着し、昇格への不満や、働き方を縛られたくないという考えから減りがちだった管理職になりたいという人も増えてきた」と、加奈氏。シニア層やサポート職の女性社員がリスキリングを経て、デジタル人材として活躍するようなケースも出てきており、女性社員の約7割が管理職を目指す専門性を求められるキャリアコースを選んでいる。
さらに、評価を決める際にも時間と多角的な視点を入れることで多様な働き方でも適正に評価されるという職場の安心感醸成を目指す。同社が社員評価にかける期間は1~2か月に及ぶという。部門長が面談などを通じて評価するだけでなく、各部門長には社員の評価理由について、全役員やほかの部門長が参加する10人ほどの人事評価委員会で説明することが課されている。他の担当役員や部門長から意見も出され、さまざまな視点が入る。人事評価委員会の運用を始めた2017年ごろには、全社員の評価を固めるまで3日間かかったこともあったという。
「社員に納得感を持ってもらうために、ほかの部門の幹部の視点も大事になる」と由佳氏。
■世代を超えて社内の結束を育む施策
同社は事業拡大もあり、社員数が2015年の125人から、現在約160人に増えている。10歳代~30歳代までの社員の割合は58%に上り、若返りも進む。キャリア採用は昨年約800人の応募があり、大手で実績を積んだ20~30歳代の高度人材も入社している。
こうした若い世代が増える中で、同社では、忘年会や社員旅行に加え、社員の家族も参加できる「フジワラわくわく祭り」など、交流の機会を重視する。部門や世代を超えて、互いの「ライフ」の側面に触れる機会を作っている。ライフ面を知ることによって、会社全体で、個々の社員に対する休暇や残業への配慮・気配りの風土が定着する。

年に1度3日間連続の休暇がとれる「リフレッシュ休暇」、1時間単位の有給休暇、育児休業とは別に配偶者の出産に合わせたパパ休暇――。時短勤務といった制度はもちろん、ライフイベントを控えた社員が多くなる中、福利厚生制度も整える。会社を支えてきたシニア社員に対しても看護休暇や定年後の再雇用制度などもそろえる。「若い世代だけでなく、シニア層も、大切な『人財』で、高い専門性を生かしてもらえるようにしていきたい」と加奈氏。ライフ面をサポートする制度とともに、社内の風土・雰囲気が、働き方改革の実効性を支えている。
また、社員のエンゲージメントを高めるために始めた社員向け調査も大きな役割を担っている。「かつては上司や評価への不満など『会社が嫌いなの?』と思うような回答ばかりだったが、今は前向きな業務改善提案や感謝の声が寄せられるようになった。質は様変わりした」と由佳氏は驚きを隠さない。社内イベントの開催に制約となったコロナ禍では、社員の結束の弱まりがデータとして示され、経営層が危機感を持つきっかけになったという。
加奈氏は、「会社のビジョンはトップダウンで決定したが、ビジョンを実現するための環境づくりの施策の多くは社員の声を起点にしてやってきた。課題に対し経営層で考えた“仮説”について、一度は社員に投げかけてフィードバックを受け、また投げかけることを繰り返してきた。その重要性は今後も変わらない」と語る。
加奈氏は、「多様な個を活かし、社員の想いを結束させながら企業価値をさらに高め、2050年に向けた壮大なビジョンを実現したい」と、今後も社員と向き合いながらの会社経営を続けていく考えを強調する。