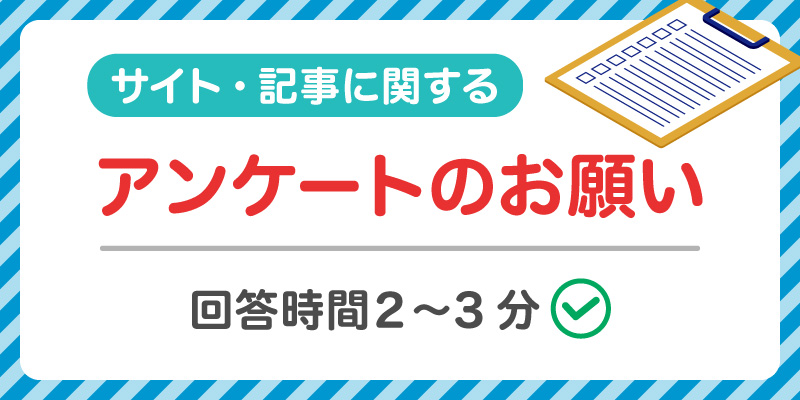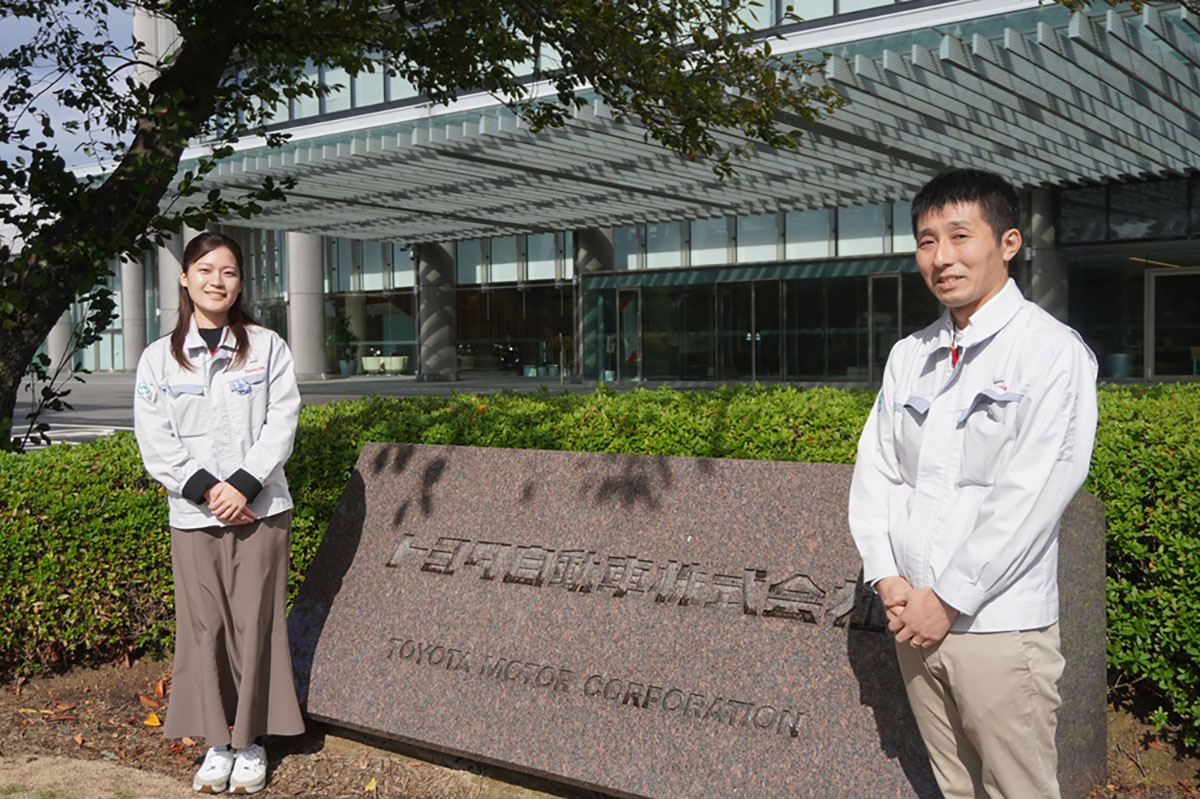残業を減らして接客の質、業績に変化
株式会社銚子丸
忙しいのは、お昼時と夕方。多くの人が休む土日祝日は書き入れ時。店舗は多いほど売り上げは増える。外食チェーンの宿命の中で、すしチェーン大手銚子丸が、働き手の暮らしに寄り添い、多様な働き方を受け入れようとしている。残業時間を念頭にした給与のあり方を見直し、原則休みとする店休日を導入。そして、男性中心だった板場(調理場)への女性登用を進める。人手不足が深刻化する中で離職率の改善を進める銚子丸の取り組みについて、石井憲社長をはじめ、女性店長の鈴木晶美・川口店 店長、人財採用課の菅野恵美マネージャーに話を聞いた。
記事のポイント
- 残業時間を減らしつつ、給与を維持。社員に余裕が生まれ、スキルアップで生産性向上
- 研修の充実でオールマイティ社員を増やし、職員・店舗間での柔軟なサポートを実現
- 全店で一律の店休日を設定(商業施設内店舗など一部除く)。公休数を従来の104日から112日に
- 離職率は12.6%から7.5%へ
- 多様な人材を生かすことで、新業態にも挑戦

■残業代が「生活給」という従来の考えから決別
――働き方改革の進捗はいかがですか。
石井社長)働き方改革には、前社長の石田満・特別顧問が2017年10月に着手しました。外食チェーンにありがちですが、当社もお客様の笑顔や満足度のためにと、長時間労働を美徳とするようなところもありました。人手がかかり、労働集約的なところはどうしてもありますが、人口減少社会の中、離職対策の面からも働き方改革は不可欠です。
営業時間は、2018年ごろから見直してきました。閉店時間はかつての午後10時から段階的に早め、今は午後8時30分ラストオーダー、午後9時閉店です。
営業日も、2018年に年中無休をやめました。契約上の営業条件がある大型商業施設内の店舗などを除き、原則として全店舗が休業する「店休日」を設けました。本人が休みでも、店舗が営業していると、問い合わせ等で連絡が入り、「休んだ気がしない」といった声が以前からあったからです。2024年は、3日連続の店休日を定期的に設け、1年間に20日程度店休日を作りました。
鈴木店長)社員が休みをとれるようになって、職場の雰囲気が変わりました。パートから正社員となって働いてきましたが、働き方改革前は、魚をさばいたり、握ったりする技術に対して、職人の厳しい指導があり、店内にピリピリした雰囲気がありました。休みが増えて会話が弾むようになって、強面の職人の表情も柔らかくなったように思います。
菅野氏)重労働が減ったことで働きやすくなった面もあると思います。働き方改革が始まる2017年の女性社員は全社で20人ほどでしたが、いまは約80人が働いています。休みがとりやすい雰囲気が定着したことで、生活に合わせた働き方ができるようになった結果だと思います。

――社員の意識も変わりましたか。
石井社長)働き方改革当初は、残業の削減や休みが増えることに、反発がありました。残業代が生活を維持するために欠かせない給与という「生活給」というような認識が、社内にあったからです。残業時間が減ると、収入が減ってしまう。生計を考えると、働く時間は長い方がいい、残業が減ったり休みが増えたりすれば、各家庭にとっては稼ぎが減るというような印象があって、反対だったんです。
会社としては、残業で稼ぐのではなく、スキルアップで給与を高めてもらうよう、給与制度も見直し、社内の雰囲気も変えていきました。
半期ごとに各社員に業務目標を掲げてもらい、会社として成長をサポートしていくようにしています。
菅野氏)固定時間外手当は、かつて70時間相当でしたが、現在は30時間相当に削減しました。一方で、スキルアップによって、ホール(接客)から調理、握りまですべてをできる店舗社員を増やすよう、会社としても研修制度を充実させました。給与面だけでなく、社員が互いをサポートし合える職場になれば、一人への負担が減って、残業時間は減り、それぞれが働きやすい、休みやすいお店作りができていると思います。
■離職率が12.6%から7.5%に改善し、売上高は増加
――営業の日数や時間を減らして、売り上げへの影響はどうですか。
石井社長)外食チェーンは、「日銭商売」と言われることもあります。店を開けられるのであれば開けていた方が、売り上げが増えるからです。出店を増やして規模を追求してきた歴史があります。
しかし、人の採用や定着を考えれば、人手不足の時代において変わっていかなければいけません。銚子丸でいえば、1店舗あたり4~5人のスタッフを配置する必要があります。お店作りには、人材の定着が欠かせません。
働き方改革は、人材の採用、定着という面では大きな効果が出ています。離職率は2016年の12.6%から24年は7.5%に改善しました。新卒採用は年15-20人程度、中途採用年35人と順調です。
配膳ロボットの導入や回転レールの廃止による廃棄食材の削減など店舗運営の見直しも並行して進め、営業時間の削減や店休日の拡大があっても、売上高は働き方改革以前の2016年5月期から10%超増やすことができています。
転職が当たり前の時代ですが、同業他社から転職したいという声を聞くようになったのは、光栄です。
鈴木店長)残業を減らしても、スキルアップして(あらゆる店舗業務に対応できる)オールマイティな社員が増えたことで、一人ひとりが柔軟に働き方を選べる好循環も生まれました。シフトを補うことで、営業面への影響がでにくくなっています。
人手が足りない店舗には、エリアマネージャーが人に余裕がある店舗からスタッフを融通します。各店舗にオールマイティの社員がいるからこそだと思います。「板前が足りない」「接客スタッフが欲しい」――といったさまざまな事情への対応が、複数の店舗が協力し合うことで対応できます。

■「社員の思いを付加価値に会社を成長」
――出産や子育てといったライフイベントの中にいる若い方たちの働き方にどう対応していますか。
菅野氏)ライフステージの悩み事は常につきものだと思います。そうした声を聞くことができ、途中でキャリアをあきらめずに、定年退職を迎えられるような職場づくりや制度を整えていく必要があります。
鈴木氏)店頭で働いていると、働く人たちからの不満は、もちろんあります。大事なことは、その声をしっかりと店長まで上がってくるようにする風通しの良さだと思っています。それを反映して、店舗運営することで、お客様に余裕を持ったサービスができるのだと考えています。
石井社長)ライフスタイルも多様な時代になっています。銚子丸においても、新規採用や中途採用、パートからの正社員登用、さらには地域限定の社員や時間制限の社員などさまざまな人が働いている。あらゆる人に、「銚子丸で働いていてよかった」と思える制度、環境を会社が作っていくことだと思っています。
社員の成長は、銚子丸のサービスの充実につながります。社員の思いは、お客様に伝わっていくものだと思っています。
規模拡大による売り上げも大事ですが、社員のお客様への思いという付加価値が生み出す力、稼ぐ力を大切にしていきたいと考えています。
――女性活用にも力を入れているそうですが、社員の暮らし、ライフに寄り添うために、どのような取り組みを進めていきますか。
菅野氏)2027年に女性店長30人を目標にしています。
休日や育児休業など、ライフイベントを抱えていても店舗で働きやすい環境は整ってきています。パートから正社員を目指す人も増えていますので、女性向けの研修を作るなど会社が正社員化をサポートするキャリア面の環境も整えていきたいと考えています。
石井社長)大きな魚をさばくとか、どうしても力仕事のところもあります。気合で乗り越えるには難しいところがあります。だからこそ、女性でも店長がやりやすい環境を整えたり、新業態を考えたりするのが、経営側の役割だと思っています。
これまで寿司の板場は、男性職場とされてきましたが、女性が持つ心配りだったり、気配りだったりという面をうまく取り入れていくことができると思います。
働き手の暮らしを考えながら多様な人材を取り入れることで、人手不足時代の中でお客様に新しい価値になると考えています。