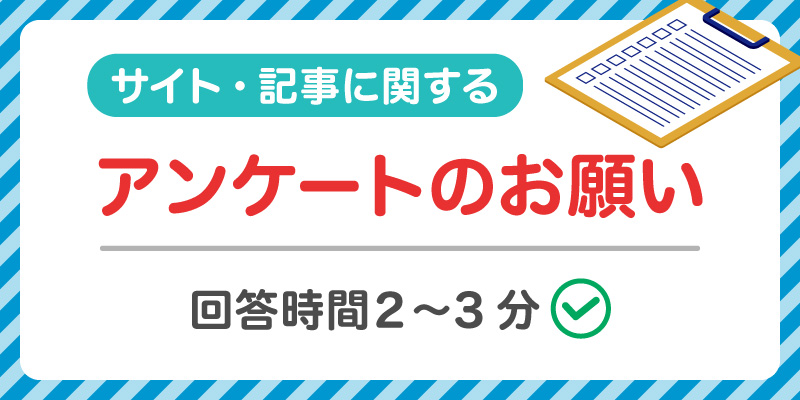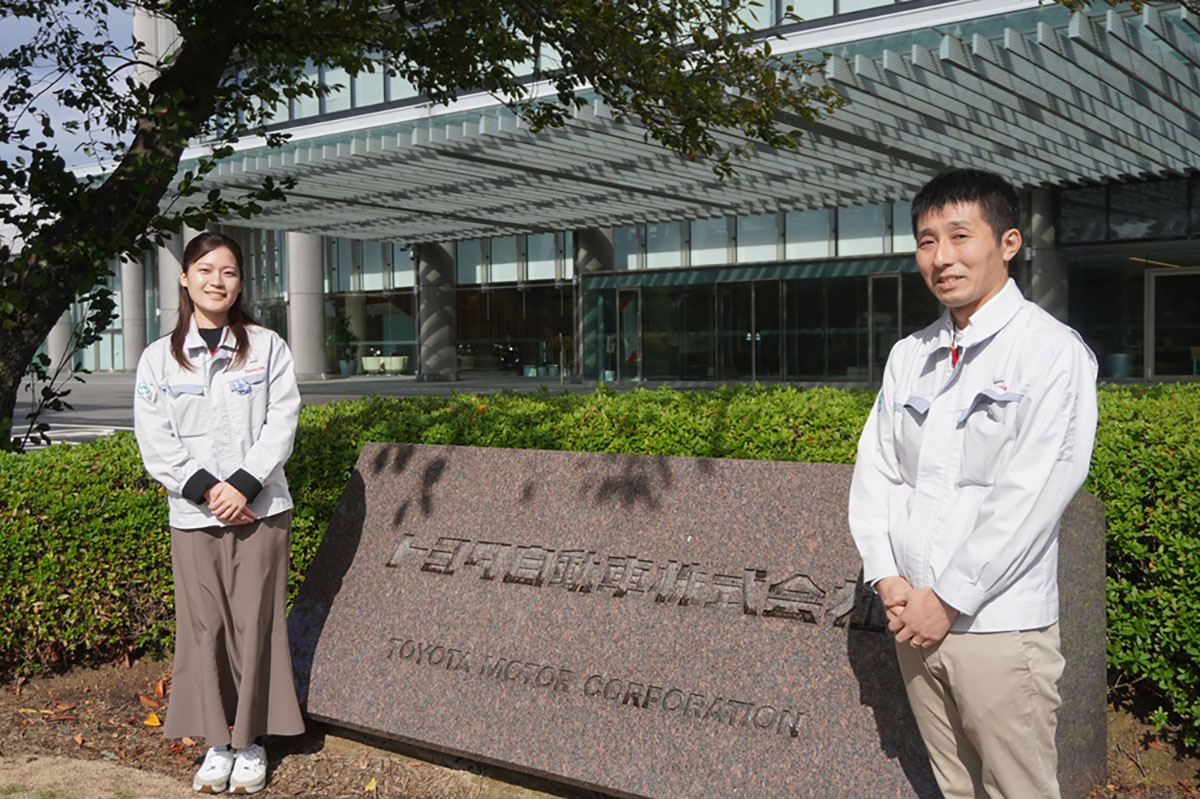社員の5つのwell-being実現を目指す人財戦略
住友生命保険相互会社
キャリアを中心において、フィジカル(心身)、ソーシャル(社会)、コミュニティー(地域)、ファイナンシャル(資産)の5つのウェルビーイング(well-being)を一人ひとりの社員が実現できる会社を目指す住友生命保険。会社でのキャリア形成だけでなく、人生においても社員のwell-beingを支えるのは、なぜなのか。取り組みの中心にいる同社の山田哲之・人財共育本部事務局エグゼクティブフェロー兼人財共育本部事務局長のほか、自らも2回の育休取得を経験した宮本優衣・人事部人事室主任、今後のライフイベントが視野に入る福澤紫・勤労部勤労室主任に話を聞いた。
記事のポイント
- 社員一人ひとりの5つのwell-being(キャリア、フィジカル、ソーシャル、コミュニティー、ファイナンシャル)を会社が支援
- 部署ごとに月1回ウェルビーイングミーティングや、部署を超えた交流機会をつくる「シャッフルランチ」で、社員がキャリアとライフを考えるきっかけを提供
- 部署ごとのコンピテンシー(好事例に基づく行動特性)を示し、仕事を属人化せず、社員が望む休暇や異動を実現しやすい環境を整備
- 社長のメッセージに加え、管理職への研修を繰り返して、風土を醸成

■キャリア「会社と社員が目指す姿を明確に」
――人財戦略を掲げている理由を教えてください。
山田氏)日本では長い間、効率化や収益化、コンプライアンス、正確かつ確実といった点が重視され、会社、世の中全体が効率化、削っていくという方向の意識が根強くなっていたように感じていました。そうした中で、2021年ごろから、チャレンジする、主体的、自律的に社員がwill(意思)を発揮できるような職場づくりを目指そうと、経営と人財戦略の連動を意識して職場環境、キャリア、評価制度を作ってきました。
――具体的にはどのようなことから始めましたか。
山田氏)各事業部の企画部門(25部門)を中心に対話を進め、コンピテンシー(好事例をもとにした行動特性)を部門ごとに作りました。スミセイコンピテンシーという会社全体の方向性を示す土台の上に、4500人の総合キャリア職ならではの職種別コンピテンシー、そして各部門ならではの専門コンピテンシーを作成し、会社が目指す姿を「見える化」。社員が目指す姿をはっきりさせ、人事制度に落とし込みました。
エンゲージメントも数値化し、分析しました。社員が会社を誇りに思ったり、この会社を推奨したいと思ったりする気持ちや、福利厚生や人間関係といった環境、職場満足度との因果関係を調べました。
福利厚生や生産性の向上を目指す「WPI(Work Performance Innovation)」といったものは、以前から充実していましたが、それを社員が活用し、キャリアwell-beingを中心とした5つのwell-being(キャリア、フィジカル、ソーシャル、コミュニティー、ファイナンシャル)を実現できるようにするためです。
たとえば、昨年から物価高などを踏まえて社員の暮らしを応援するために支給しているウェルビーイング手当(2024年度月1万2000円、2025年度月1万7000円)や、自社のサ―ビスである健康増進サポートのVitality(バイタリティ)と連動した現金支給もそうです。社員には、キャリアプラン研修の中で、人生を振り返り、どんな価値観でキャリアを持っていくのかを考えてもらう機会も設けています。国家資格のキャリアコンサルタントも約40人社内に配置し、キャリアについて、どのように考えたらいいかわからない社員にも対応しています。
――その原動力は、何でしょうか。
山田氏)社長の愛情のほかにないと思います。
制度は、時の流れとともに形骸化することが多いですが、社会福祉に貢献するという生命保険という本業そのものが「愛情」、利他の精神ですので、それが会社に浸透しています。
■型でなく、繰り返しの研修で「浸透」
――社長メッセージの徹底ですか。
山田氏)われわれは「徹底」という言葉は使わず、「浸透」と言っています。
なぜなら、「徹底」と言い出すと、フレームありきになってしまいます。型にはめると形骸化してしまいます。それでは、社員一人ひとりの価値になりません。「人財」でなくなってしまう。コンピテンシーを浸透させることで、一人ひとりが役割を果たせるような環境を作ることが大切です。
職務を属人化するのではなく、役割をつくる。パーパスに対する役割であって、job(仕事内容)でなく役割であることをコンピテンシーで明確にしています。
それによって、人事部や勤労部が提示するフレームの使い方を示すことができます。
■ライフ「必要な休みをとれる職場の風土づくり」
――育休をはじめ、社員のライフイベントへの配慮はどのようにしていますか。
宮本氏)男性の育休取得率は、4年連続で100%を達成しました。男性が育休をとることが当たり前になったことで、社員の働き方や家族との向き合い方も変わってきたような気がします。その結果、育休をはじめ誰もが必要な休みを取れるように、お互いを思いやる雰囲気づくりはもちろんのこと、仕事を属人化させない意識が高まったり、休暇前の同僚への引継ぎが丁寧になるなど、行動レベルでの良い変化もどんどん出てきているように感じます。
また、当社には、社員のライフイベントへの配慮の一環として、家族の転勤があった場合に自分もその転勤先近辺に異動希望を出せる「ファミリーサポート転勤制度」があるのですが、実は、こうした制度を活用いただく際にもコンピテンシーが役立っています。コンピテンシーが明確化されたことで、異動先での自分の役割がよりイメージできるようになり、その結果、異動希望しやすくなるといったこともあるようです。

――社員のライフを支えることが会社の生産性や価値を高めていると実感していますか。
山田氏)正直にお話しすると、生産性が高まるかどうかは、現時点ではわかりませんが、そうなると思って“根こそぎ”やっています。
いまの日本では、非財務価値が財務面でもプラスになっているとは言いがたいです。ですので、所属長は悩ましいと思います。だからこそ強いリーダーシップで会社の文化・風土を作るという、とんでもない努力が必要だと思っています。だからこそ、管理職が部下をサポートするんだという決意が必要で、リーダー、管理職の共育へ労力を相当かけています。
我々の取り組みは、チャレンジだと思っています。
人が育てばリーダーが生まれてくる。やらなかった領域にチャレンジし、成功まで頑張ることによって次のリーダーが生まれてくる。受け身で優秀な人より、「やりたい」という多少の跳ね返りの強い人間の方が1年後に10倍の違いが出ます。さまざまな要因によるものではありますが、結果を見れば、2024度の業績は最高益ですし、新卒採用にもいい傾向が見られています。
2021年以前からの取り組みも含めれば5-10年はかかっていますが、風土改革につながっています。
宮本氏)当社は、不妊治療やPMS、男女の更年期症状など幅広い層の健康課題に対する職場の風土づくりを支援する「Whodo整場(フウドセイバー)」も提供しています。職場の風土づくりは簡単なものではないですが、当社でも例えば「男性の育休100%」という一昔前では想像もできなかったことにチャレンジしたのをきっかけにさまざまな良い変化が見られた事例もありますので、これからも様々な企業と一緒にチャレンジしていければと思っています。
――社員のライフにどこまで踏み込むかは難しさもあるように感じますが、いかがでしょうか。
福澤氏)2023年の新社屋の移転を機に始めた、社内で普段関わりのない社員と一つのテーブルを囲んでランチをする「シャッフルランチ」は、新たなコミュニケーションを生んでいます。仕事の話だけになりがちな職場で、それ以外の情報を共有し、アイデア・ヒントを得るきっかけになります。
私生活について話すことに抵抗があるという社員もいると思いますが、それはまだコミュニケーションが足りない結果かと思います。
ウェルビーイングミーティングやシャッフルランチといったことを重ねることで、徐々に変わっていくと思います。
宮本氏)ウェルビーイングミーティングは、ハートミーティングというかたちで2011年から部署ごとに実施してきました。だいたい月1回のペースで、社員同士で私生活も含めたコミュニケーションをとっていますが、「人生」や「生活」に関する話は、世代を超えた共通の話題として盛り上がりやすいので、コミュニケーションの促進にもつながっていると思います。
会社が設けた機会が、社員のライフの考え方を整理する手助けとなっていると感じています。

山田氏)大企業は多くのところが同じような人事のフレーム(制度)を持っています。
大事なことは、使うことに対しての抵抗感がないかどうかです。
制度の活用に、逡巡するような風土ではいけません。
住友生命が未来永劫、継続する、サステナブルであるために最も大切なことは、人、社員でしかないと、思っています。
社員に自分のwell-beingを実現してもらうことが必要です。昨年から始めたウェルビーイング手当も、物価高などで経済的に厳しくなる中で、5つのwell-beingを達成してもらうためです。ベアではなく、社会とのつながりや自分自身のライフへ使ってもらうというメッセージ性を込めています。