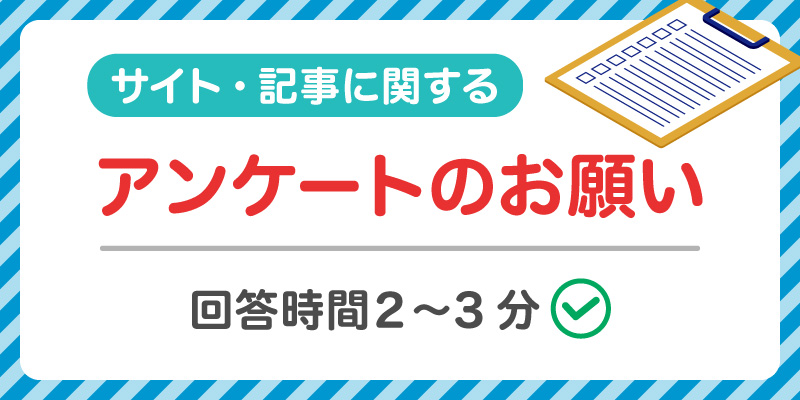終わらない家事を「わりきり」で、仕事と家庭に余裕
アナウンサー 政井マヤさん
フリーアナウンサーとして活躍する政井マヤさん。出産を経て母として家事に追われながら、仕事も続け、どんなに疲れていてもなかなか家事支援サービスに踏み込めなかった一人でもある。心身の限界を感じて、すがりつくように頼んだ家事支援サービスから得たものは、家族と笑顔でいる時間と、万全の気持ちで向き合える仕事に対する余裕だった。家事支援サービスを利用するまでの壁や、使ってみて感じた使い方のコツについて話を聞いた。

【略歴】
政井マヤさん
メキシコ生まれ神戸育ち。上智大学で社会学(ジェンダー論)を専攻。フジテレビ勤務を経てフリーに転身。ラジオパーソナリティ、コメンテーター、司会、モデレーターとして活動。娘1人息子2人の母。
――家事支援サービスの利用について教えてください。
利用するようになったのは第2子が生まれたときくらいだったと思います。いま、長女が高校3年生、長男が中学3年生、次男が小学2年生なので、15年ぐらい前ですね。子供が小さい頃に、週1回、多いときは週2回ほど、定期的に来てもらっていました。
掃除だけでなく、ベビーシッターのような感じで子供と一緒に留守番をしてもらう、ということもありました。
■使い始めるときに感じた「引け目」
――利用のきっかけは?
友人が家事支援のサービスを使っていていいな、と思いながらも、「うちは豪邸でもないし」とか、「みんな頑張っているんだから私ももっと頑張らなきゃ」と考えて、なかなか踏み切れませんでした。
ただ、2人目を出産したあと、1人目の時はやりくりできていた家事、育児、そして仕事が回らなくなって、てんてこ舞いになってしまったんです。神戸で父の介護をしていた母に来てもらうこともできず、泣きそうになりながら電話をして、「こういう(家事支援の)サービスをお願いしようと思うのだけど」と、相談したのを覚えています。相談が必要なことではなかったのですが、自分で決める勇気がなかったのだと思います。
背中を押して欲しくて電話をしたのですが、母は私のことを心配しながらも、第一声は賛成の言葉ではありませんでした。ごく普通の家庭でそんなサービスを使うのは不相応と思ったようで、「義理のご両親はどう思われるかしら?」と。家事を人にお願いすることで私がどう思われるか、そちらを心配してくれていました。
家事をお願いするといっても1週間にたった1日、数時間だけなのに、私も母も大袈裟なほど引け目を感じていました。それでも「もうしんどくて…」と泣いている私に、最後は寄り添ってくれました。

――家事支援サービスを使うのに理由を探したんですね。
おかしいですよね。私自身、メキシコがルーツなので、お手伝いさんがいる文化にはむしろ慣れているんです。祖母の家にもいつも住み込みのお手伝いさんがいましたし。それなのにいざ私自身の為に家事支援サービスをお願いしようと思うと、「みんな頑張っているんだから、私も頑張らないと」と。日本の働く母親像への思い込みのようなものがあったのかもしれません。
でも、日本のお母さんはそもそも頑張り屋さんで、スーパーウーマンすぎるとも思うんです。統計でも明らかに日本の男性の帰宅時間は遅く、家事や育児の分担が難しい。夕食のバリエーションも品数も豊富だし、お弁当だってとても手がこんでいますよね。ジップ付きのビニール袋にバナナとクラッカーとチョコ、なんて日本ではできないですものね。
もともと私は家事が得意でないのに、自分に多くを求めすぎていたな、と思っています。「ここは外部のサービスに補ってもらうところ」、と堂々と利用したらよかった、と、今になって思います。
■家事支援サービスの方も一緒に子育て
――利用を始めてみて、ご家族は。
夫は、もともと家事も「その時にやれる方がやろう」というフラットなスタンスでしたし、家事の能力も高いので、決して私一人で頑張っていたわけではないのです。それでも長期の現場仕事も多く、いない時は全く家にいない。その上で私の忙しい時期が重なってしまうと大変でした。
次第に、夫も家事支援サービスが入るペースに慣れて頼りにするようになりましたし、お互いの分担もうまく回っていたと思います。
子供たちの方は、すぐに家事支援サービスの方に慣れて、「○○さんが来る日だね!」と喜んでいました。家が綺麗になることが嬉しかったみたいです。
利用を始めてからは、私自身は本当に助けられました。2時間くらいでキッチンをはじめとした水回りを丁寧に磨いてくれて、掃除機をかけて、シーツの交換までをパパっとやってくれました。その手際の良さはまさに「プロの技」でしたね。週に1回来てもらうだけでも、部屋がリセットされてそこまで散らかりにくくなりました。仕事で疲れがたまっているときも、「明日にはお掃除が入るから、今日の家事は最低限にして子供とゆっくり向き合おう」と思えました。
よく育児と仕事の両立といいますが、私は家事と育児、そして仕事の三つ巴だと思っています。そのうち仕事と育児は代わりがきかない場面が多いけど、家事は誰がやってもほぼ同じ。いちばん頼みやすいと思うようになりました。
そう割り切れるようになってからは、時間的にも、体力的にも、何より精神的に余裕がうまれて、結果として私の笑顔も増えたと思います。それが子供にとって一番大きかったと思います。振り返って、3人の子育てが大変なときは、母、義理の母など親族はもちろんですが、信頼できる家事支援サービスの方もチームの一人として、一緒に子育てをしてもらっている感覚でした。
私はお料理の利用はなかったのですが、産後に自治体の補助が出る食事サービスを使った友人は、年配の方が作ってくれる料理が美味しく、また優しく接してもらえて「もう一つ実家ができたみたい」と感激していました。
■家事代行サービス利用は、気持ちの「リフレッシュ」
――家事代行サービスで余裕が出たことでよかったことは。
自分ではやりきれない家事があっても、残りの家事を家事支援サービスの方にバトンタッチすることで、仕事の事前準備のために少し早く出かけたり、子供が小さくて夜眠れなかった時には体力温存させてもらったりできました。家事をする時間が減るだけでなく、その時間はとても有効に使えた気がします。
自分が元気になって家族と楽しく過ごせるとか、仕事に集中できるとか、家事の負担が減る以上のプラスアルファの効果があったと思います。なので、自分たちの収入の中でその費用対効果をどう捉えるかなんだと思います。
部屋が散らかっていると女性は男性よりストレスを感じやすい――。そんな海外のレポートを読んだとき、思わずうなずいてしまいました。
週1回の部屋のリセットで、私自身が健やかに過ごせるというのはとても大事なんだな、と思います。ジムや趣味にお金をかけてリフレッシュするのと同じように、家事支援サービスを使ってリフレッシュするというのもいいのではないでしょうか?

――家事支援サービスで、抵抗感や困ったことはありましたか。
夫は最初、家に他人が入ることに少し抵抗感がありましたね。
なので、最初のころは、プライベートとパブリックのゾーンを分けて、リビングやキッチン、水回りを中心に「ここをお願いしますね」という形でやりました。次第に、信頼関係ができることで、だんだん心配はなくなって、家中をお任せすることができました。
また、最初のころは、片付けしてもらった後に、キッチンの小物などの収納場所が分からなくなって、「あれはどこにしまってくれたんだろう?」ってなったこともありましたね。でも、困ったことがあれば、都度話をして、指示を明確にしたり、自分のやり方を見てもらったりすることで、解消できました。
立ち入らないで欲しい部屋や触ってほしくない場所(作業中のデスクの上など)を伝えたうえで、貴重品は鍵のかかるところにしまうなど、誤解をうまない工夫も必要だと思います。
何より、事前によくリサーチをして信頼できる人を探すことが大切かと思います。簡単ではないのですが、一度見つかれば頼れる存在になると思います。
――なかなか利用に踏み切れない方たちにアドバイスを。
年末の大掃除などにまずは単発で利用してみるといいかもしれません。レンジフードやクーラーの清掃、窓掃除など、普段の家事では手が回らないところから、お願いしてみるとか。きっかけとして、家族やパートナーから、母の日や誕生日などに、家事支援サービスをプレゼントするというのも素敵なアイデアだと思います。
何度か使ってみてよかったら、自分たちのライフスタイルに合わせて、毎月や毎週など決まったペースで来てもらうと、それがルーティン(習慣)になって、サービスも含めた新しい家事と仕事のバランスが見えてくると思います。
私の長女も、もう高校3年生です。キャリアや進学をいろいろ考える時期に来ています。娘に限らず、もちろん息子達も、次の世代に家事支援サービスといったサービスが当たり前にあって、みんなが無理をせずに仕事や育児を楽しめる環境があるといいな、と思います。
また、私自身もそうでしたが出産年齢が高いと、親の介護と子育てが重なってしまうダブルケアという状態になる方もいると思います。いろんな状況があると思いますが、アウトソーシングできるところは利用して、大変な時期を乗り切ってほしいと思います。そしてそういったサービスが受けやすくなるような自治体や会社からのサポートも増えるといいなと思います。