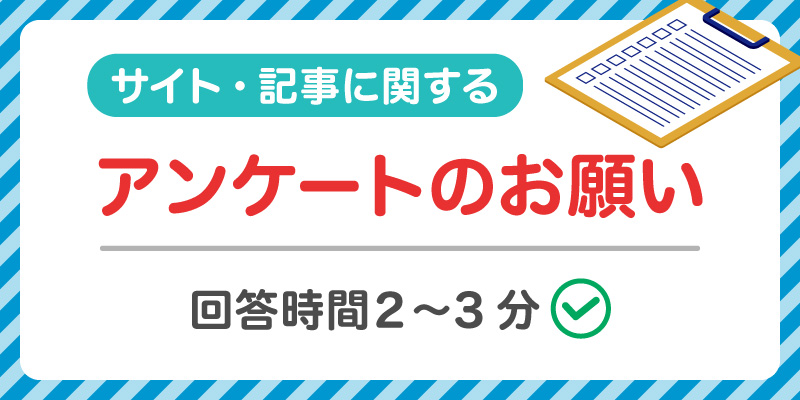キンタロー。さん、都内イベントで家事支援サービスに支えられたお笑い芸人活動を語る
当サイトで家事支援サービスについてインタビューに応じてくれたお笑い芸人のキンタロー。さんが、10月19日に東京都内で開かれたイベントに登壇しました。「家事支援を活用したイマドキの“キャリア”と“ライフ”」と題したトークセッションで、キンタロー。さんは「プロにお願いすることで、苦手な片付けと向き合わなくてよくなりました。かつらや衣装も整理整頓され、仕事の効率も上がりました」と話し、忙しい中でも生活や仕事の質を上げる家事支援サービスの魅力を語りました。

■片付け・掃除サービスとの出会い
今回のイベントでは、日本テレビの田中毅アナウンサーを司会に迎え、キンタロー。さんと東京大学多様性包摂共創センターDEI共創推進戦略室の中野円佳准教授が、キャリアやライフに対する新しい価値観のあり方や、家事支援サービスを取り入れることで、生活の質が向上することなどについて、それぞれの立場からお話されました。
キンタロー。さんは、社会人経験を経てお笑いの道に進み、2012年末に「あっちゃん」のモノマネで一躍人気者になりました。もともと家事の中でも掃除は苦手。テレビ番組で、何度か片付いていない部屋が紹介される中、テレビ番組の中で現在も掃除をお願いしている家事支援サービスの方と出会いました。キンタロー。さんは、「片付けも相性があります。私はリバウンドしづらい片付けをしてくださる方に出会い、部屋をきれいに保てるようになりました」と言います。それ以降、長らく家事支援を使い、結婚・出産を経て2児の母となっても、「家事支援はなくてはならない存在です」と話します。
■共働き、支える存在が必要
中野さんは、日本は諸外国に比べて、男性の有償労働時間が長く、女性が有償労働も無償労働も行っている現状を紹介しました。働く人が仕事をして帰宅し、ご飯を食べて睡眠を取り、また働きに出る状況を整えることなどを社会学で「再生産労働」と言います。中野さんは、「高度経済成長期は、働きに出る労働者を妻の内助の功が支える構図でした。キンタロー。さんも、『かつらはここだよ、出張行くなら用意してあげるよ』と支えてくれる人が欲しいということだと思うんです」と指摘。キンタロー。さんも「そうそう」と共感しました。

また、家事支援を使わない理由としては、「所得に対して価格が高いと思われるため」「他人に家の中に入られることに抵抗があるため」といった声が多くあります。中野さんは、全国家事代行サービス協会が設ける「安全・安心」「機能同等性」「接遇」などの基準を満たした認証制度を紹介しました。キンタロー。さんも「認証制度があると安心して任せられますね」と話しました。
■「サービス、どんどん取り入れたい」
キンタロー。さんは最後に、「家事支援サービスをうまく組み合わせて、どんどん取り入れていきたいと思っています。まだ利用する人が少ないですが、利用者が増えれば、サービスのバリエーションも増え、更に利用者も増えるいい循環が生まれる。どんどん利用する人が増えて欲しいです」と語りました。

このイベントは、読売新聞が社会課題の解決や潜在力の掘り起こしを通じて、日本経済の新たな成長につなげようと始めたプロジェクト「目覚めよJAPAN」の一環として開催され、経済産業省がこのフォーラムに協賛しました。