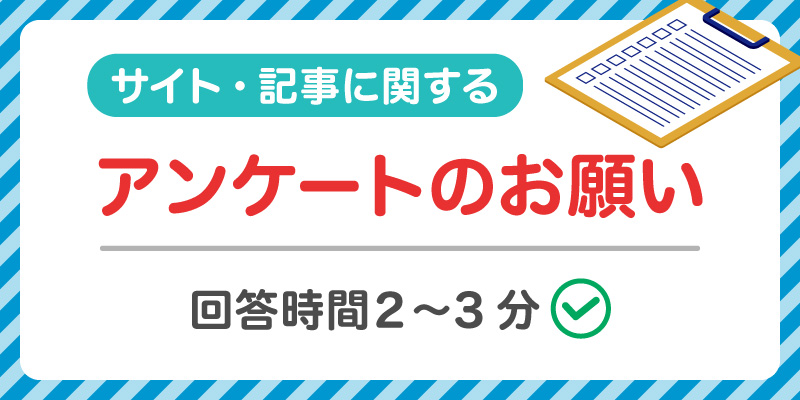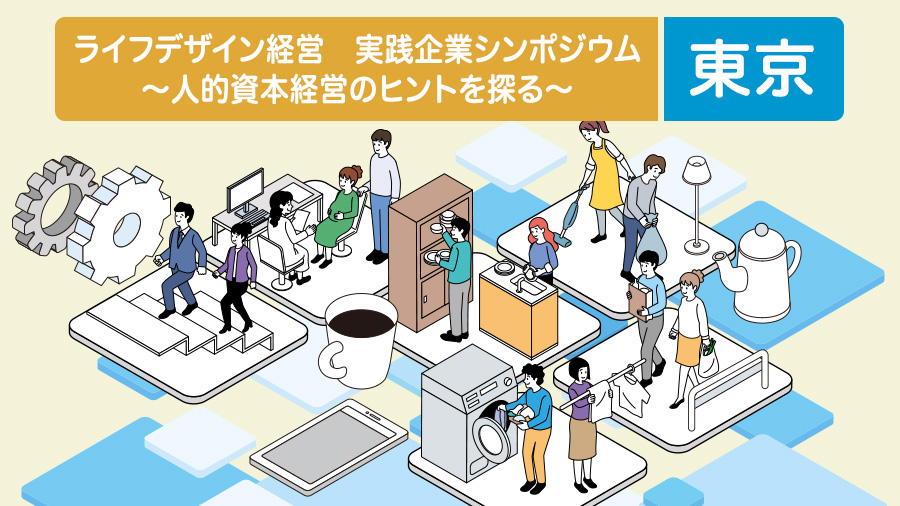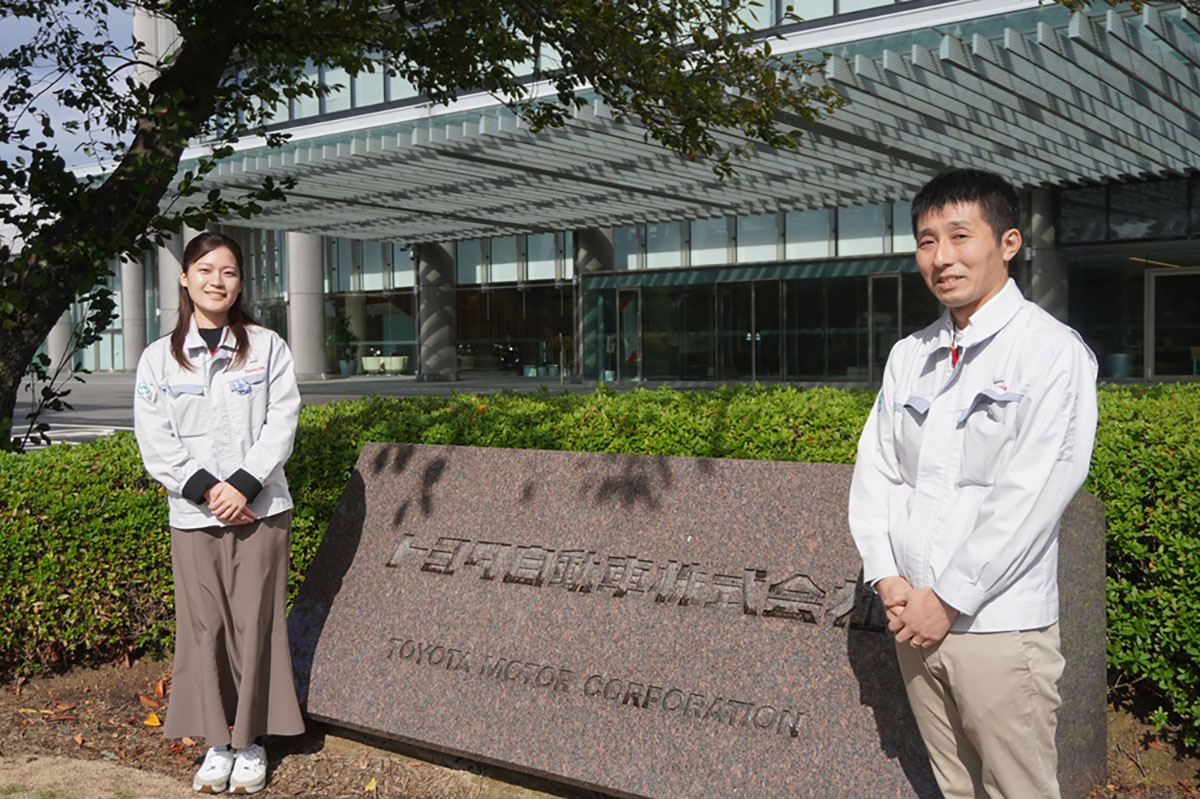働き方改革のうえで女性活躍を目指す理由
株式会社日本旅行
日本旅行は、2024年から働き方改革の推進に大きく舵を切っている。コロナ禍という業界全体に対する逆風を糧に、人的資本経営の重要性に気づかされたという点が大きい。今年、社員全体に対する女性比率が男性を上回り、さらにその傾向が高くなる現状を踏まえ、当初は「女性活躍の推進」を掲げたが、その取り組みは性別、年代問わない「働き方改革」として進めてきた。「働き方改革を実現した先に、女性活躍がある」。総務人事部の女性活躍推進・働き方改革推進担当の三好幸代部長は、こう語る。
記事のポイント
- 世代、性別、勤務場所、ライフスタイルなどのバランスを意識した人選で、業務、働き方の問題点・課題を洗い出し
- アクションプランをつくり、「働き方改革」を社内横断プロジェクトに
- 女性活躍推進のためにも、中堅、管理職・支店長の長時間労働対策にも目線
- 属人化した業務の見直し、「個」から「チーム」へシフト
- 福利厚生制度の認知・利用の格差を是正する情報発信

■「女性活躍推進」担当として着任して気づいた“意識の違い”
「新設する女性活躍推進担当のポストをやってほしい」――。出産、子育てを経験しながら、個人旅行部門で営業畑を歩んできた三好氏にとって、2024年の人事異動は想像していなかったキャリアチェンジだったという。個人旅行営業現場は比較的女性が多く、支店長の半分以上が女性と、すでに女性が活躍しているイメージがあったからだ。三好氏は、「こんなに女性が活躍しているのに、なぜ『女性活躍』なのかと思った」と、振り返る。実際に、日本旅行は、2023年12月、厚生労働省が認定する、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が特に優良である「プラチナえるぼし」を取得していた。
しかし、三好氏は辞令を受けて、その理由に、気が付いたという。それは、社内にあるキャリアに対する男女間のギャップと、女性が活躍する職場の偏りだったという。
当時、三好氏は大阪勤務で、大学生の長女がおり、京都に暮らしていた。東京で勤務になれば、京都からの通勤は難しい。職場で異動のあいさつをすると、男性社員からは「おめでとう。頑張ってね」と本社への異動を祝われるが、女性社員からは「娘さんは大丈夫?」と心配された。いざ、本社に出社すると、総務人事部はじめ管理部門の管理職は男性ばかり。長らく女性の多い営業職にいた三好氏にとっては、当時の社長が女性活躍の推進を掲げた理由も納得だった。
一方、職場ごとに女性比率が大きく異なる社内の実態や、社内にあるキャリアに対する男女の認識の違い。「やるべきことは、女性活躍の前に、『働き方改革』なのではないか」。社長に相談し、三好氏の肩書は、「女性活躍推進・働き方改革推進担当」となった。
■プロジェクトメンバーの平均年齢は40歳
三好氏が着手したのが、職場・業務の課題の洗い出しからだった。各部門・エリアの各支店、各部署から人選し、横断プロジェクトをスタートした。職場だけでなく、性別、年代のほか、結婚や出産といったライフイベントの経験の有無も考慮してメンバー20人余りで構成した。職場や人事制度への課題抽出だけでなく解決策の立案まで出せる人財を意識した結果、平均年齢は40歳、想定より高くなった。「こうしたプロジェクトは若手を中心となることも多いが、解決策の立案、行動までしっかりとできる巻き込み力のある人財にこだわった。若手や女性ばかりでなく、会社を支える中堅の声も大事」(三好氏)という信念からだった。
毎月グループワークを実施した。業務や職種、課題感が似通った部署の人同士で議論を深め、知恵を出し合うことで、問題点と解決策を明確にした。2~3か月かけて出てきたのが、仕事が特定の社員に依存する「属人化」や、デジタル化に対応していない取引といった職場ごとにある特有の事情によって社内的な制度があっても取り入れられない働き方改革の「壁」、今ある制度の周知・理解不足など、解消すべき点が浮き彫りになったという。
さらに、意外だったというのが、若手も含め多くの社員から上がったある声だったという。
「支店長が一番大変だと思う」「管理職の長時間労働が常態化している」――。 三好氏は、若手や女性へのサポートも重要視しつつ、「社員構成で最も多く会社を支えている50歳代の男性管理職の存在が大きい。その層への対応が必要」と考えたという。

■コロナ禍が転機となった「個」から「チーム」へ
旅行業界にとって大逆風となった2020年から2023年のコロナ禍は、くしくも日本旅行にとって働き方改革を推し進めるきっかけになった。在宅勤務といったDXへの対応の必要性だけでなく、特定の社員に頼った「属人化」のリスクも顕在化したからだ。コロナ禍では個人旅行はもちろん、企業・組織の需要や大規模な会議・催しといった団体旅行、修学旅行といった教育旅行も軒並み止まった。
売上のけん引役だった敏腕営業担当者が打撃を受ける中、全国・国内外に地の利を持つ強みを生かして旅行業の枠を超えて地域の社会課題解決に取り組む事業を全社で推進した。中央省庁や自治体の事業を受託する新たなビジネスにつながり、新たな収益基盤になった。三好氏は、「営業成績が評価基準という旅行営業と異なり、事業期間が長く、複数の人間が協調する事業に挑戦する中で、仕事に対する考え方も変わった」と語り、「敏腕営業担当者の存在は今でも大きいし、稼げる人は大事で、一定の仕事の属人化は認める。しかし、そこに依存しない、新しい発想が社内に定着するきっかけになりました」と、その重要性を口にする。
時間や場所の制約に対応しなければいけないコロナ禍が根本的な発想を変え、複数の人財がそれぞれの能力を発揮することで、チームが結束して生産性が上がることもわかり、新たな働き方に即した人事評価などの見直しの検討も進めたいという。 「チームとしてパフォーマンスが発揮できれば、新たな可能性が生まれる。営業の組織化を定着させたい。そのためにも社員一人ひとりの個性を認めていくことが大事だと思います」と、三好氏。
■持続性を保つために社内制度の見直しと、情報発信
プロジェクトメンバーで洗い出した課題に対するアクションプランを作り、経営陣への提言を行った。「新しい制度の導入だけではなく、今ある制度のアップデートや利用促進も重要な要素」と、三好氏。
また、2024年からは社外サービスを活用し、女性に特化しない、年代・性別を超えた福利厚生サービスも導入した。健康に対する悩みやリスキリングなども支援する。福利厚生は、育児といった若い世代へのイメージが強い中、悩みの多い「介護」をテーマにした情報発信やセミナーを増やすことで、幅広い年代にライフイベントや福利厚生に関心を持ってもらうようにしている。三好氏は、「自律型の組織にするには、風土、意識、制度の3要素で手を打つ必要があります」と語り、約4000人のグループ社員の一人ひとりに働きかける重要性を説く。
数年後を見据え、「価値観アップデート研修」や、管理職や全社員向けに向けた「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)研修」など多様な人財を受け入れる研修を繰り返す。「若い世代だけでなく、いまあるシニア層や中堅クラスが持つノウハウやスキルをいかに共有化し、持続的な企業成長につなげていかないといけない危機感があります」と三好氏。
さらに、同社は、全ての社員が働きがいを持って長く活躍してもらえるよう、社員それぞれがライフデザインをどう描くかや、会社が個々の社員にどう寄り添えるかを重要視している。三好氏は、「若手社員の意見を聞くと、大半が生活や人生を充実させたいと考えている一方、その具体的イメージを描き、アクションしている人はそれほど多くない」と指摘したうえで、「ライフも含めたキャリアデザインへのリテラシー向上こそが、「働き方改革推進担当」という役割におけるミッションだと強く感じています」と続ける。
「働き方改革と言うと、営業にブレーキをかけるものと誤解されがちだが、ゴールは生産性向上や社員のエンゲージメントにつなげ会社にイノベーションを起こし業績を上げること」(三好氏)。挑戦は続く。