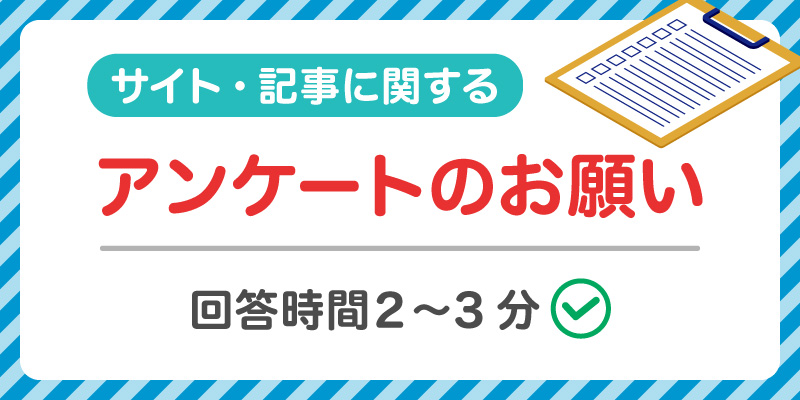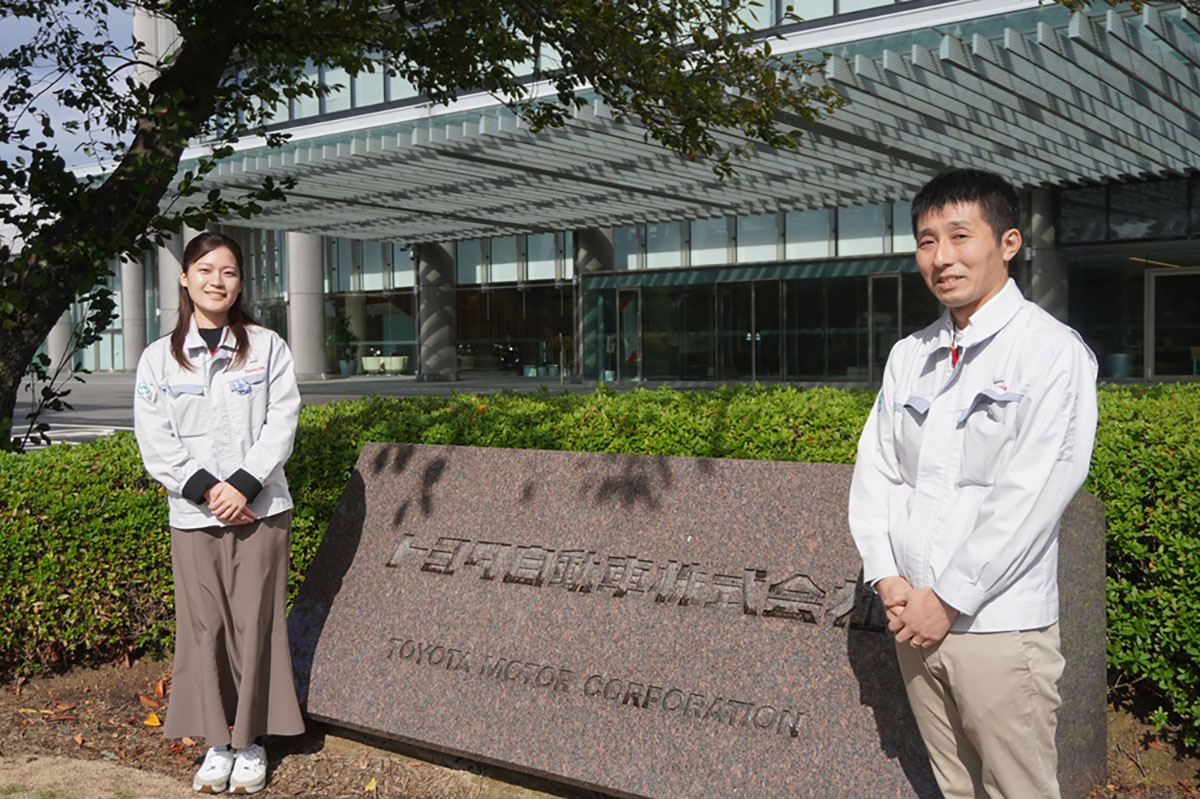ライフスタイルに合わせたシフト選択制が生むイノベーション
株式会社オンワードホールディングス
23区やICB(アイシービー)などのブランドを展開するアパレル大手オンワードホールディングスは、2019年から社員の残業削減と休日取得を促進する「働き方デザイン」に取り組んできた。その背景には、社員のイノベーションを引き出す狙いがあったという。具体的にどのような取り組みを行い、成果はあったのか。アパレル業界という華やかなイメージのある世界の一方で、上下関係が厳しいなど「体育会系」の企業風土と呼ばれる会社に起きた変化とは。人財Div.ダイバーシティ推進Sec.の青木莉菜・課長代理(32)に話を聞いた。
記事のポイント
- 店舗スタッフ含め約9割が女性の職場が、体育会系の体質から変わるきっかけになった「カエル会議」
- 全社員にアンケートをとって見直した勤務体制で、子育て社員のフルタイム勤務が増加
- 配偶者、パートナーも巻き込んだ「プレパパママセミナー」や、管理職や職域を意識した研修によって根付かせたキャリアとライフへの理解
- 上層部の意向だけでなく、現場からの声が上がって新規事業がブラッシュアップされる会社に

■華やかなイメージとは裏腹に「体育会系」だった会社が変わったワケ
オンワードホールディングスは、社員の働き方改革プロジェクト「働き方デザイン」を2019年夏から始めた。「ファッションをデザインするのと同じように、社員一人ひとりが働き方をデザインできるように」(青木さん)と、改革ではなく「デザイン」と名付けてプロジェクトをスタートした。
その軸となったのが、「カエル会議」だったという。「早く帰る」「働き方を変える」――。さまざまな意味を込めたこの会議は、現在も形を変えながら、部署ごとに継続している。
おおむね10人前後のチームで、個人が仕事(キャリア)だけでなく私生活(ライフ)も含めて、「ありたい姿」を共有する場所としている。スキルを向上したいといった目標から、自分自身の趣味の充実に向けた仕事との両立でもいいという。それぞれがその時点の自分にとって「ありたい姿」を掲げて、PDCA(Plan=企画、Do=実行、Check=評価、Action=改善)を回していく。カエル会議の狙いについて、青木さんは「一人ひとりの社員に働き方をデザインしてもらう機会を作るためでした」と話す。
アパレルという華やかなイメージとは裏腹に、メーカーではデザインから設計、生産、在庫管理、さらには店舗運営に、イベントなどと社員は平日、休日、昼夜問わず仕事に追われることも多い。働き方デザインを進めたのは、保元道宣社長の「ライフスタイルが変わる中で、イノベーションを生み出すためには長時間労働を改善していかないといけない」という強い思いだったという。
■働き手の声で変えた勤務制度で時短勤務が減少
カエル会議では、ルールを作っているという。他人の意見を否定するような発言はしないことや、意見を出すときは上司も部下も同時に意見を出す。なるべく職位に関係なく、業務上の改善点や悩みを共有しやすい雰囲気を作るという。 残業時間が多い。休日がとりにくい――。社員の本音が出ることによって、制度や社内の風土も変化してきた。
その一つが、2022年秋から導入したシフト選択制だ。基本の始業を午前9時としつつ、出勤時間を前後1時間(午前8時~午前10時)10分刻みで決められる。1日の労働時間を変えずに自分の生活に合わせて出退勤の時間を決める。「子育て中の社員は、保育園の送り・迎えで分刻みに生活しているようなところもある。自分の生活にあわせて出退勤の時間を決められることで、時短勤務だった人がフルタイムで働けるようになった人もいる。より柔軟な働き方がキャリアとライフの両立につながっている」と、青木さん。
勤務体制の見直しでは、シフト選択制以外に、全社員が共通して勤務する時間帯コアタイムを設定しつつ労働時間の範囲で就業時間を決める「フレックスタイム制」や、従来通り一律の勤務時間を定めることも選択肢とし、社員アンケートをとった。働きやすさを重視して、社員の声を聞いて制度化した。
さらに、制度だけでなく、社員が働き方をデザインする本来の趣旨を実現するため、環境づくりにも力を入れた。全社員に対し、出退勤の時間や打ち合わせ予定などスケジュールを記入するよう求めた。それぞれが自分の働き方を実践できるようにするためにも、予定を「見える化」するためだ。青木さんは、「スケジュールに『考え事をする時間』などと設定する人もいる。スケジュールを共有することで、配慮してもらえるし、連絡する側も連絡がつかない理由がわかれば心理的なストレスが減る。店舗は夜まで営業していることもあり、かつては営業担当者に夜も問い合わせが入り、休みづらい雰囲気があった。スケジュールを共有することによってそれぞれの働き方を尊重する風土が社内にできた」と話す。こうした環境を保つため、人事部は社員に対しスケジュールの共有について定期的に徹底を図るようにしているという。

■休みを取得したい人が取得できる環境づくり
オンワードが大切にするポイントの一つに、「心理的安全性」がある。社員がキャリアやライフに対する悩みを抱えたときに、抱え込まずに安心して相談できる環境づくりだ。2022年には、経営幹部に対して数日間にわたる研修を実施した。座学だけでなく、座学を踏まえて各部署においてチームメンバーの強みや弱み、悩みをヒアリングし、その結果を持ち寄り、改めて研修を開いて、幹部同士に意見交換させた。幹部自身にチームメンバーの本音を引き出す難しさを体験してもらい、どのような聞き方や姿勢であればチームメンバーからキャリア、ライフの両面で話をできるかを考えてもらったという。
育児休業についても、子供の出生予定の有無にかかわらず社員とその家族を対象に「プレパパママセミナー」を開催して、職場の理解浸透を図る。さらに、全国の店舗社員を意識して、店舗と向き合う営業担当者や地域を統括するエリアマネジャーらを対象にした研修も実施する。「取得する人だけでなく、職場全体で取得しやすい環境を作っていきたい」と、青木さん。
傘下の事業会社オンワード樫山の社員は約2800人。店舗社員も含め、9割弱が女性だ。平均年齢は40歳代前半と、出産や子育てといったライフステージに直面している社員が多い。店舗スタッフにおいては、特に働くママが多い。オンワードでは百貨店など同じ商業施設内に点在していた複数店舗を統一する店舗の複合化を進め人員配置の柔軟性を高めるとともに、休みが取得しやすい職場の雰囲気作りが欠かせないという。
■多様性を認める中で生まれた新ブランド、新業態
カエル会議をはじまりに定着してきた社員が本音を語り合いやすい環境は、新しいブランドや業態の創出につながっている。
2021年秋に販売を開始したブランド「UNFILO(アンフィーロ)」は、デザイナーにも、商品企画や販売戦略を考えるMD(マーチャンダイザー)にも子育て中の20-40歳代の男性社員と女性社員がいる。多様な人材がかかわることで、伸縮性や通気性など機能とファッション性を併せ持つ「機能美」を追求するコンセプトにあう商品開発を行っているという。「アンフィーロ」は発売開始以来2桁の成長を続け、青木さんは「働き手のリアルな声、いろんな意見が合わさってイノベーションが生まれている」と、話す。
経営トップ層の発想で始まった「23区」や「ICB」といった各ブランドの垣根を超え、横断的にそろえる店舗「オンワード・クローゼットセレクト」も社員の声で、改善が進む。各ブランドにはそれぞれのイメージがあるため、当初は、社員からは不満の声もあったが、社員の声を反映しながら試着・購入できる取り寄せサービスなどを組み合わせ、業績を支える存在になっているという。
アパレル業界は、商業施設の営業時間に合わせた店舗運営や催事への対応などで不規則になりがちだ。「体力を求められる仕事でもあるが、社員がそれぞれの働き方をデザインできるようになったことで、体育会系の結束力といったいい側面と、柔軟性によって生まれる創造力が合わさっていい雰囲気が生まれている」と、青木さん。さらに、人事部の立場として、「育児だけでなく、今後の日本社会において欠かせない介護とも両立して働けたり、社員が社外でスキルアップできたりする制度や風土を作っていきたい」と、さらなる働き方デザインに取り組む意欲を見せる。
<コラム>シフト選択制が可能にした推し活ライフ
今回、取材に協力してくれた青木莉菜さんも、シフト選択制をきっかけに、キャリアとライフを両立する「働き方デザイン」を実践している一人だ。
青木さんは2016年に入社し、ECサイトや営業、生産管理などを経て、2022年から人事部に所属する。入社当時は、まだ働き方改革プロジェクトの前で、「入社式の翌日はいきなり倉庫出勤で、汗をかきながら在庫管理の仕事。キラキラした部分は本当に一部で、体育会系の会社と実感した」と、振り返る。
しかし、現在では、シフト選択制の導入などもあり、自分自身で働き方を“デザイン”できるようになった。趣味も大切にしやすくなり、人気ロックバンド「氣志團」の推し活にも力が入る。ライブ当日は、始業を午前8時に設定することで、午後4時40分に退社できるようにしている。ライブ会場の開場時間午後5時30分に向けて駆けつけるという。「グッズ購入もライブの楽しみ。開場時間には行きたいです」。青木さんの表情が、人事制度を語る人事部の担当者の顔からシフト選択制で充実感を感じる一人の社員の顔へと変わった。