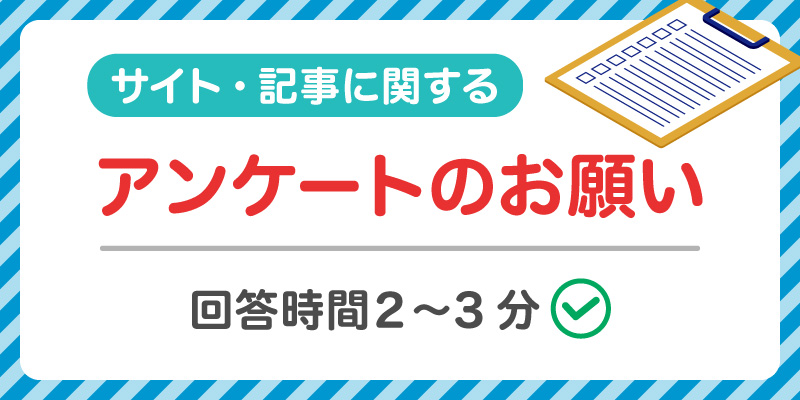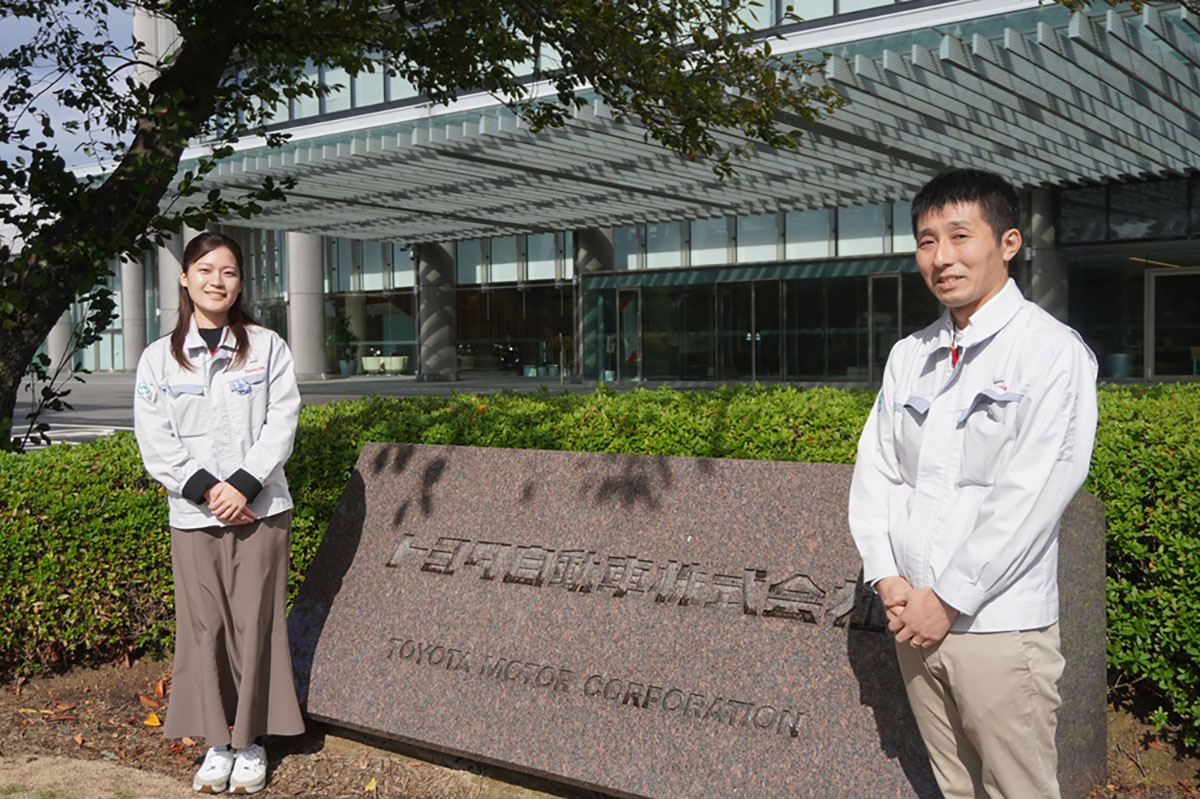サントリーのDNA「やってみなはれ」を実現するライフサポート
サントリーホールディングス株式会社
サントリーは、社員に失敗を恐れず挑戦を求める創業の精神「やってみなはれ」の実践を追求するうえで、人本主義を掲げ、さまざまな取り組みを進めている。たとえば、働き方の多様化に向けた重要な項目の一つとして、男性社員にも育児休職を働きかけ、社員が自分らしく働ける組織を実現してビジネスに生かそうとしている。それを支えるために取り入れられているのが、マネジャー層とメンバー層の間をつなぐ綿密なミーティングや計画策定、そして「ONE SUNTORY One Family」の一体感を醸成する社内イベントだという。自らも1児の母となって育休取得し、2歳の子供を育てながらフルタイムで働く人財戦略本部の佐藤珠希さんに、サントリーの取り組みや理念を説明してもらった。
記事のポイント
- 男女を問わず子供の誕生を控えた全社員を対象に、「仕事と育児の両立計画書」の作成を必須とし、マネジャーとの面談を実施。出生前後の業務を部署全体でサポートする
- 子供の出生後の復職時にも面談を行い、社員が望むワークとライフのあり方を共有する
- 第1子誕生予定の社員には「Welcome Baby(ウェルカムベビー)セミナー」を実施。取得予定メンバーの所属長も参加し、育休や子育て家庭に対する理解を職場に浸透させる
- シッター費用の補助も充実。保育園に入れなかった場合や、急な残業や出張などの緊急時に使える補助もある
- 職場以外で社員が交流する機会も設け、職場の一体感を作り、挑戦する「安心感」を醸成
■仕事と育児の両立計画を策定、上司と面談
サントリーでは、男性社員、女性社員問わず、子供の誕生を控えた全社員を対象に、「仕事と育児の両立企画書」の作成を必須としている。2022年から男性社員の育休取得率100%を宣言する中で、子供の誕生前後の働き手をサポートする体制を整える狙いがあるという。
計画を策定することで、育休取得時に、業務をフォローする同僚に円滑に仕事内容を引き継いだり、職場での負担が増えすぎないように調整したりできるという。社員本人だけに策定を委ねるのではなく、マネジャーが育休の前後に面談を行うことで、本人の育休取得タイミングの希望や働き方、職場で期待するサポートの内容などを丁寧に拾い上げることができる。
第1子誕生の社員は仕事と育児の両立に戸惑いやすいことを踏まえ、過去に育休を取得した男性社員の事例などを紹介する「Welcome Babyセミナー」を実施し、所属長も参加させている。「職場全体で育休に対する理解を広げるため」(佐藤さん)という。出生後18か月間に取得できる男性の育休取得率は2024年末に100%を達成した。

■「働きたい」に応える会社のサポート
子育て世代に対する育休後のサポートの手厚さも、同社の特徴と言える。
育休明けの復職後の所属長との面談や、育休後のフォローアップセミナーで復職をサポートする。「働きたい」という産後の女性社員の意欲をサポートするため、保育園に入園できなかった場合には、会社や共済会からベビーシッター費用を支援する「つなぎベビーシッター制度」を設けている。さらに、保育園の入園の有無にかかわらず、子供の病気や緊急時に手助けしてもらいたい社員のためには、「緊急時・病児ベビーシッター制度」で一部費用を補助している。営業職などに復職した社員が、時間的制約が多い得意先業務においても柔軟に利用することができる。1年4か月の育休後にフルタイムで復職した佐藤さんは、「残業を推奨するわけではないが、『柔軟に働きたい。業務後のイベントに参加したい』という社員が子供を安心して預けていられる環境がある」と、話す。中学生の子供の学校行事や習い事に対応するための休暇制度もある。1子の場合は年間5日、2子以上なら10日、休暇取得できる。
■多様性が生むビジネスの持続性
サントリーには、創業者である鳥井信治郎氏の言葉「やってみなはれ」の精神が根付いている。失敗を恐れることなく、新しい価値の創造を目指し、諦めずに挑み続けるという意味で、社員の意欲をベースとする「人本主義」の底流には、この「やってみなはれ」の精神がある。
「社員が個性や能力を発揮し、失敗を恐れずに挑戦していく。それによって企業も成長していくと考えています」と、佐藤さん。キャリア形成の一環で、各社員には難易度の高い「チャレンジ目標」の設定も求めている。単年目標に関わらず、難しい目標を自らたて、そのプロセスや成果を人事考課において加点評価するものだ。また、2015年からは、「有言実行やってみなはれ大賞」を設け、担当業務以外も含め、社員の多様な新しい挑戦を評価するコンテストを始めた。社員の個性を引き出す機会と位置付ける。
こうしたチャレンジ精神や個性を生かした取り組みを社員から引き出すうえで、育休といったライフのサポートも無関係ではないという。
育休を取得することで、子育てを実感したり、買い物に出たり、家事を主体的にしたり――。男性社員も職場以外の価値観や流行に触れることで、気づきが増える可能性があるからだという。同社は、酒類から清涼飲料、健康食品など幅広い製品を手がけるメーカーで、佐藤さんは、「年齢・性別問わず多様なお客様がいらっしゃるなかで、当社の社員も様々な価値観を持たないと、社内の多様性は広がりません。男性社員も育休を取得することでビジネスにも多様な価値観を取り入れることが出来ると思っています」と語る。

■社員の選択肢を増やす「10年3仕事」
サントリーはキャリア形成の一環で、入社から10年目までに3つの異なる仕事を経験すること、またその過程で必ず一度は部門や領域をまたぐ異動を経験してもらう「10年3仕事」を実施している。佐藤さん自身も、2011年の入社以来、埼玉の営業部署から、缶チューハイなどのRTDのマーケティング部署を担当、その後、広域営業本部の企画担当も担った。育休を経て、人財戦略本部で働く。
「(ライフイベントの多い)若いうちに、いろいろな業務を経験することで、キャリアの柔軟性が高まり、ライフイベントに応じた選択肢が広がります。復職後も安心してキャリアとライフの両立ができます」。フルタイムでの復職を決めた理由を、佐藤さんはこう語る。
働き手の安心感は、職場の空気づくりにもある。サントリーグループの全世界の社員を対象としたウォーキングイベントや家族も参加できるソフトバレーボール大会を行う。「職場とは違う、普段の上司や同僚の姿、別の一面を垣間見ることができ、交流も生まれる。そういったONE SUNTORY One Familyの一員である安心感の中で挑戦意欲を高め、そこから生まれる新たな価値の創造が経営戦略の実現につながっていく」(佐藤さん)からだ。
多様な職場で一人ひとりが個性と能力を発揮することで、会社に新しい可能性を生む。「上司や同僚とファミリーメンバーとしての安心感があるからこそ社員が自分らしく挑戦できるのだと思います」。佐藤さんは、育児期に限らず、どんなライフステージにある社員でも生き生きと働ける職場環境の背景をこう説明する。